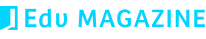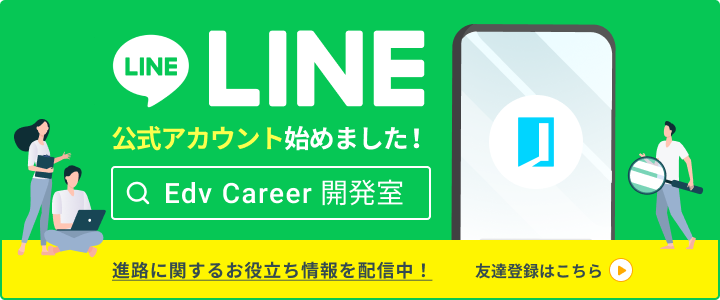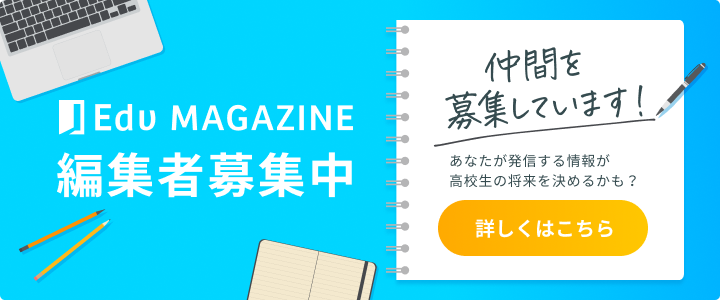お正月にもらったお年玉やバイトのお給料、あなたはどう使っていますか?友達と遊ぶお金や欲しいものを買うのもよいですが、もし銀行口座に貯金しているのなら、その一部を「投資」してみてはいかがでしょうか。
実は今の時代、現金で貯金するよりも株式や国債といった金融商品に投資したほうが、長い目で見ると増えやすくなっています。そして民間の金融機関では、未成年が投資を始められる環境も整っているんです。期間限定のものもあるので、メリットやデメリットを学んで、今こそ投資を始めてみませんか?
なぜ投資がおすすめなのか?
そもそも、なぜ今「投資」をするとよいのでしょうか。それには「資金を増やす」という金銭的なメリットと、将来の暮らしに役立つ知識としてのメリットがあります。
「貯める」よりも「増やす」時代
かつて「資産は銀行に預けるもの」という考えが常識でした。定期預金金利が5%だった時代には、1000万円預ければ30年後には4000万円を超える(1年複利で計算した場合)こともありました。しかし「超低金利時代」と呼ばれる現在では、預金によって増える金利はごくわずか。同じように1000万円を預けても、利息0.01%では30年間でプラス3万円程度にしかなりません。
この超低金利は2016年に導入された「マイナス金利政策」の影響によるもの。民間の金融機関が日本銀行に預けている預金金利をマイナスにする(=預ければ預けるほど減ってしまう)という政策で、各金融機関は日銀への預金額をできるだけ減らすため、預金者への金利を非常に低く設定しています。
このような政策により「銀行に預けるよりも投資によって資産形成を行うほうが得をする」という構造ができあがりました。
金融リテラシーが身に付く
投資というと失敗して多額の借金を抱えたり、株価の上下に一喜一憂するギャンブルのようなイメージがあるかもしれませんが、実は投資こそ金融リテラシーを身に付ける最短の方法といえます。
自分のお金をどう増やすか考えることは、どの金融商品を選ぶかという選択であり、有効な資産形成をするための基礎となります。お金との付き合い方を正しく身に付けることで、将来の家計管理に役立つことはもちろん、お金に関するトラブルから身を守ることにつながります。
社会や企業のトレンドに敏感になる
金融は社会情勢や経済界のトレンドと切っても切れない関係にあります。アフリカの政治不安が石油価格に影響を与えたり、新技術の発表が特定の業界の株価を一気に押し上げたりということはよくあることです。
そのため、投資をやっているとおのずと世の中の情勢にアンテナを張るようになります。ビジネスに関する話題はもちろん、各国の政治や経済、社会問題についても幅広い知見が身につくでしょう。
主な投資の種類
一言で投資といっても、投資の対象や方法によってさまざまな種類があります。まずは未成年も取引ができる一般的な投資について解説します。
株式投資
株式投資はもっとも一般的で、始めやすい投資です。企業が事業を運営するうえで必要とする資金を、株式を買うという形で出資します。株式投資で得られるメリットは、株券を売却して得られる「売却益=キャピタルゲイン」と、企業が得た利益を株主に支払う「配当金=インカムゲイン」、そして企業が株主に独自サービスや商品を提供する「株主優待」の3種類です。
投資信託
個人で運用するのではなく、複数の投資家から集めた出資金を専門家や証券会社がまとめて運用する形態の投資です。国内外の株式に加え、国債や不動産も含まれ、リスクとリターンのバランスによってさまざまな銘柄から選ぶことができます。小口で複数の金融商品に分散投資できるため、少ない金額から始められるかつリスクを分散できるメリットがあります。
国債
国が発行する債権を購入し、一定期間が経過した後に元本と利息を受け取ることができます。国債は元本保証と最低金利保証がされており、リターンが低い分リスクも少ない、安定した投資対象です。
投資の流れ
どんな金融商品であっても、投資用の口座を通して取引するのが基本です。金融商品によってやり方はさまざまですが、大まかな流れからつかんでいきましょう。
元手を準備
数百万円、数千万円という大金がなくても、投資は始められます。投資対象によって元手として準備するべき額は異なりますが、数百円から始められるものもあります。目安として1万円くらいは初回の投資額として準備しておきましょう。
また、投資は一度きりのものではなく、継続して資金を投じるものです。初回の元手をいくらにするかに加えて、「毎月いくらまでなら投資に使えるか」という点を考えておきましょう。
投資用の口座を開設
まずは投資専用の証券口座を開設します。株式投資であれば証券会社に、投資信託であれば証券会社または銀行など金融機関、FXであれば専門の取引会社に口座を開設します。主要な証券会社の口座なら、株式、投資信託、FXなどほとんどの金融商品の取引が可能です。
銘柄を選定
口座を開いたら、どの金融商品でどの銘柄を購入するか選定します。株式投資なら今後値上がりが期待できる銘柄、投資信託ならリスクとリターンのバランスなど、選ぶ基準はさまざまです。
売買注文
投資対象が決まったら売買注文を行います。売買の流れは、金融機関や投資の種類によって異なりますが、大体の金融商品はネットで手続きすることが可能です。
まずは投資用の口座を開設しよう
証券口座の開設に年齢制限はありません。高校生でも小学生でも、極端にいえば0歳でも口座を開設できます。ただし、開設にあたって条件や必要書類が決まっています。
未成年口座を開くための条件
未成年が証券口座を開くためには、親(または親権者、未成年後見人)の同意が必要です。金融機関によっては、親がその金融機関に証券口座を持っていることが条件になっている場合もあります。また、未婚(一度も結婚したことがない)であることが条件となっている場合もあります。いずれにしても、親に無断で口座を開くことはできません。
必要な書類
口座開設に必要な書類は、一般的には下記の4点です。
- 未成年総合取引口座開設申込書(金融機関によって名称が異なります)
- 開設者本人のマイナンバーがわかる書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 登録親権者との続柄が確認できる書類(家族全員の住民票の写し)
- 登録親権者の本人確認書類
未成年口座で取り扱える商品
未成年口座で取り扱える金融商品は、一般の口座より限られています。主に取り扱いができる商品は次のような商品です。
- 国内株式
- 外国株式
- 投資信託
- 債券
- 金・プラチナ
- 貸株
- 定時為替
- その他金融機関で定められている金融商品
株式投資なら「ジュニアNISA」がおすすめ
未成年が投資を始めるなら「ジュニアNISA」がおすすめです。ジュニアNISAは、個人用の税制優遇制度「少額投資非課税制度(NISA)」の子ども版で、一般の金融商品にはないさまざまなメリットがあります。
毎年80万円まで投資が可能
ジュニアNISAでは、毎年新規投資額の80万円までが非課税枠となり、投資によって得られた配当金、譲渡益等が非課税対象となります。
最長5年間の非課税期間
非課税対象となるのは、最長で5年間。これは投資をした日からではなく、投資をした年から起算されます。12月に投資しても1月に投資しても、非課税期間の終了は5年後の年末です。
18歳まで払い出し不可
一般的なNISAと異なり、ジュニアNISAは進学や就職といった将来を見据えた資産形成という性質も持っています。そのため災害などの特別なケースを除き、18歳までは払い出しができません。
元本割れのリスクも
ジュニアNISAは投資の一種なので、当然元本割れのリスクがあります。リスクの高さはファンドによって異なりますが、低リスクとされている銘柄でもノーリスクではないことに注意しましょう。
2023年で制度が終了
ジュニアNISAは2023年12月末までの制度です。それ以降新規の買い付けはできなくなりますが、制度終了時点で20歳になっていない場合は、20歳になるまで金融商品を保有することができます。
参考:ジュニアNISA|金融庁
おすすめのネット証券会社
ジュニアNISAを始めるなら、証券会社で口座を開きましょう。ネット証券は開設が簡単で、その後の買い付けや各種手続きもスムーズにできるのでおすすめです。各社の特徴とジュニアNISA限定特典をご紹介します。
SBI証券
ネット証券最大手。一番の魅力は売買手数料の安さで、ジュニアNISAでは国内株式の取引手数料が無料です。さらに海外のETFと呼ばれる投資信託も無料。
楽天証券
ポイントサービスと連動し、グループとしての強みを発揮しています。国内株式の取引手数料が無料。
参考:未成年口座|楽天証券
松井証券
大正7年創業の老舗。国内株に強く、他社に先駆けてさまざまな制度を導入してきた先駆者でもあります。ジュニアNISAの取引手数料は無料です。
参考:未成年口座開設|松井証券
DMM.com証券
急成長中の証券会社。口座開設のスピードが早く、最短で当日に口座が開設できる点が特徴です。ジュニアNISAの取引手数料は無料。
まとめ
「お金に働いてもらう(稼いでもらう)」というように、投資は時間を味方につけるものです。将来を考えると、始めるなら早いほうがお得といえます。特に税制上の優遇措置を受けられるジュニアNISAは、期間限定なので早めの申し込みをおすすめします。ただし、あくまでも投資にはリスクがつきもの。必ず保護者の方と相談し、計画的かつ安定的な投資で将来に備えましょう。